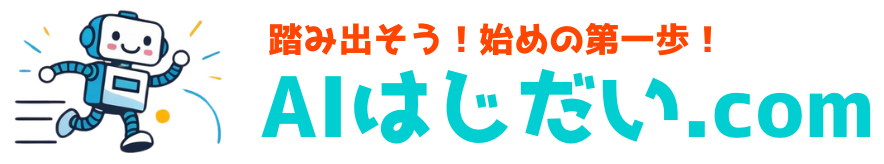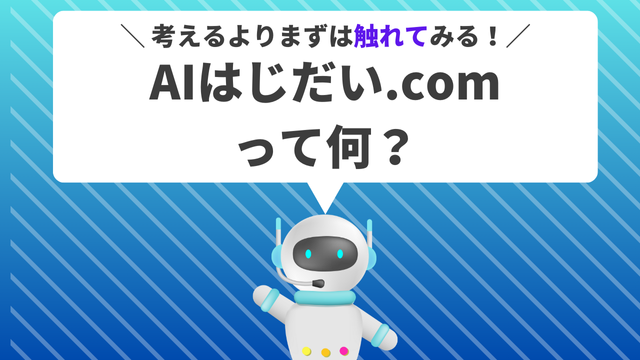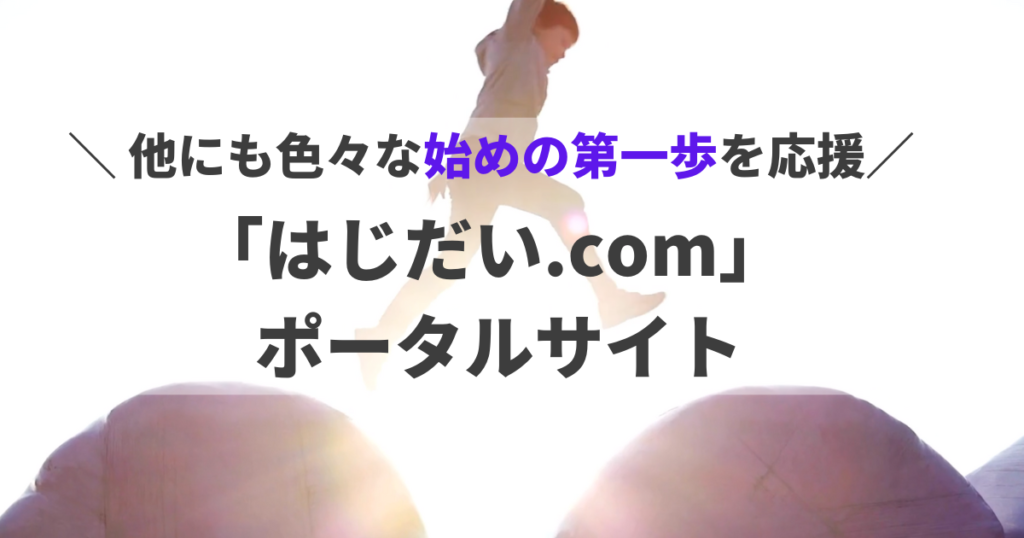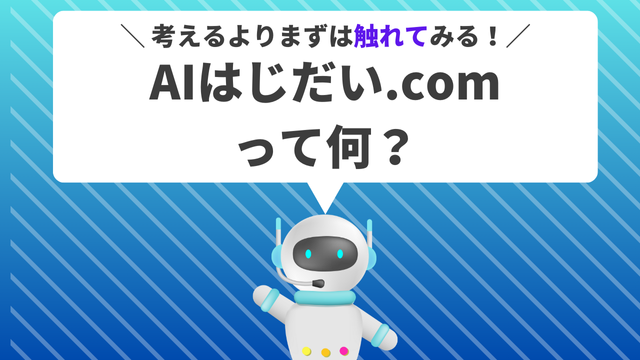# 知的財産保護のためのAIモニタリング
## すぐに試せるプロンプト例
まず、実際に使えるプロンプトを3つ紹介します。コピーして生成AIに貼り付けるだけで活用できます。
**プロンプト①:著作権侵害の可能性を調査する場合**
「私の会社のWebサイトに掲載されている『〇〇という製品の説明文』が、他のサイトと似ていないか確認してください。類似している場合は、どの部分が似ているのか、そしてどのように修正すればよいかアドバイスをください。」
**プロンプト②:商標侵害のリスクを評価する場合**
「『〇〇という新しい商品名』を検討中です。この名前が既存の有名なブランドと混同される可能性がないか、法的なリスクがないか教えてください。」
**プロンプト③:知的財産の監視報告書を作成する場合**
「当社の知的財産(特許、商標、著作権)の侵害リスクについて、月次レポートのテンプレートを作成してください。経営層が理解しやすい形式でお願いします。」
—
## ポイント① 生成AIの活用で知的財産保護が身近になる
生成AI 使い方を学ぶことで、知的財産保護がこれまでより簡単になります。従来、知的財産の監視や分析には、弁理士※1などの専門家に高額な費用を払う必要がありました。しかし生成AIを使うことで、初期段階の調査や分析を自社で実施できるようになります。
例えば、新商品の名前を決めるとき、その名前が商標登録されていないか、既存のブランドと混同されないかを事前に確認したいケースが多くあります。ここで生成AIにプロンプト(命令文)を入力することで、リスク評価を数分で得られます。
重要なのは、生成AIは「最初のスクリーニング※2」として活用するという視点です。完全に法的判断を代替するわけではなく、専門家に相談する前の準備作業を効率化できるツールと考えることが、安全かつ効果的な使い方です。
## ポイント② プロンプトの質で結果の質が決まる
生成AI 使い方の中で最も大切なスキルは「良いプロンプトを書く力」です。これは漠然とした質問をするのではなく、具体的で明確な指示を与えることを意味します。
例えば「著作権侵害がないか調べてください」というプロンプトより、「当社の〇〇製品の説明文(以下に記載)が、△△業界の標準的な説明と似ていないか、具体的に比較分析してください。類似点があれば、修正案も提示してください」という方が、はるかに有用な回答が得られます。
プロンプトを書く際のコツは、以下の5つです:
1. **背景情報を明確にする**:何の目的で何を調べるのか
2. **具体的な指示を与える**:曖昧さを排除する
3. **希望する出力形式を指定する**:レポート形式、リスト形式など
4. **必要に応じて追加情報を提供する**:関連する資料や事例
5. **修正指示をしやすくする**:「もし不足があれば追加してください」など
このように丁寧にプロンプトを構成することで、生成AIは知的財産保護の強力なパートナーになります。
## ポイント③ 実務での具体的な活用シーン
知的財産保護の実務では、生成AIが複数の場面で威力を発揮します。
**監視業務の効率化**:インターネット上で自社の商標や著作物が無断使用されていないか定期的に確認する必要があります。このとき、チェックすべき項目リストを生成AIに作成させることで、見落としを防げます。
**リスク評価レポートの作成**:新製品の企画段階で、知的財産侵害のリスクを評価するレポートが必要になります。生成AIに「〇〇という事業分野に参入するときの知的財産リスク評価」というプロンプトを入力すれば、検討すべき項目が自動生成されます。
**従業員教育の資料作成**:知的財産に関する基礎知識を社員に理解させることも重要です。「営業部門向けの知的財産侵害防止ガイド」というプロンプトで、わかりやすい資料が作成できます。
実際の生成AI 使い方として大切なのは、試行錯誤することです。最初のプロンプトで完璧な答えが得られなくても、質問を改良して何度も試すことで、徐々に望む形の出力が得られるようになります。
—
※1 弁理士:特許や商標などの知的財産に関する専門家
※2 スクリーニング:初期段階での選別・検査